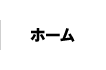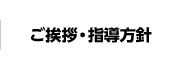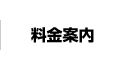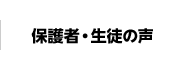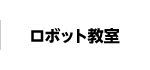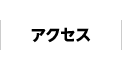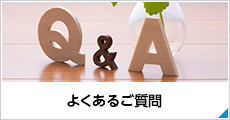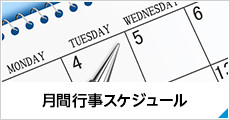カテゴリ
月別 アーカイブ
- 2025年3月 (2)
- 2025年2月 (2)
- 2025年1月 (2)
- 2024年12月 (2)
- 2024年11月 (2)
- 2024年9月 (4)
- 2024年8月 (2)
- 2024年7月 (1)
- 2024年6月 (2)
- 2024年5月 (1)
- 2022年2月 (3)
- 2022年1月 (3)
- 2021年3月 (3)
- 2021年2月 (3)
- 2021年1月 (3)
- 2020年9月 (1)
- 2020年8月 (3)
- 2020年7月 (3)
- 2020年6月 (3)
- 2020年5月 (3)
- 2020年4月 (1)
- 2020年3月 (1)
- 2020年2月 (2)
- 2020年1月 (3)
- 2019年11月 (1)
- 2019年10月 (1)
- 2019年9月 (3)
- 2019年7月 (1)
- 2019年6月 (1)
- 2019年5月 (2)
- 2019年4月 (1)
- 2019年3月 (2)
- 2019年2月 (4)
- 2019年1月 (3)
- 2018年12月 (3)
- 2018年11月 (2)
- 2018年10月 (4)
- 2018年9月 (4)
- 2018年8月 (3)
- 2018年7月 (2)
- 2018年6月 (3)
- 2018年5月 (2)
- 2018年4月 (4)
- 2018年3月 (4)
- 2018年2月 (5)
- 2018年1月 (3)
- 2017年12月 (1)
- 2017年10月 (4)
- 2017年9月 (4)
- 2017年8月 (3)
- 2017年7月 (4)
- 2017年6月 (4)
- 2017年5月 (3)
- 2017年4月 (5)
- 2017年3月 (4)
- 2017年2月 (2)
- 2017年1月 (2)
- 2016年12月 (4)
- 2016年11月 (1)
- 2016年10月 (3)
- 2016年9月 (3)
- 2016年8月 (2)
- 2016年7月 (2)
- 2016年5月 (1)
- 2016年3月 (2)
最近のエントリー
HOME > Hopeブログ > 勉強への取り組み・意識 > 勘違いから見直すべき。
Hopeブログ
< 意識の違いから生じること。 | 一覧へ戻る | 予習することで何が変わるのか? >
勘違いから見直すべき。
『勉強する』とは一言では簡単に言えますが、その中身の部分がとても大切です。
「何を勉強するのか」「どう勉強するのか」「どこを解けるようにするのか」など
具体的な戦略や目標が求められます。
いつも学校ワークは全部やってテスト期間で提出はしているのに、テストでは点数が取れない・・といった場合
・「やり終えること」が目的になっていませんか?
・「何が解けて、何が解けない」かちゃんと把握できていますか?
・間違えた問題は「どうして間違えたのか」しっかりと確認して解消していますか?
・「何でその答えになるのか」聞かれても説明できるようになっていますか?
など、ただやみくもに勉強するのでは無く、そういった意識や学習法の中で勉強しないことには成績は上がりません。
勉強しているのに成績がなかなか上がらない場合は『勉強の中身』の部分から徹底的に見直すことが必要と言えます。
とは言っても、その部分から改善していくとなると自分では気づかないところも多くて難しいので、塾の先生などに見てもらってください。
当塾でも各生徒でそういった意識などの改善が必要な子については徹底的に意識改革から指導&サポートいたします。
学習塾Hope
住之江区北加賀屋5-2-9セラ鳴門(南港病院向かい)
カテゴリ:
(学習塾Hope) 2025年3月14日 18:19
< 意識の違いから生じること。 | 一覧へ戻る | 予習することで何が変わるのか? >
同じカテゴリの記事
予習することで何が変わるのか?
現実として、予習がしっかりと出来ている子はかなり少ないです。
もちろん、その日その日で学校で新たに学んだ内容に躓くことなく順調にテストを迎えられれば良いですが、そう簡単にはいかないから塾へ行ったりしていることだと思います。
●よくある学習
①学校の授業で分からなかったり、ついていけない部分ができる
②塾の授業で聞いたり質問しながら補って解消する
ここでは①⇒②へのタイムラグが短いほど、より苦手箇所もそれほど蓄積することなくスムーズに学習が進んでいきます。
逆に、①⇒②へ移行する時間差が長くなってしまうと苦手部分が解消されないまま学校の授業は進んでいくので、どんどん遅れを取ってしまうことになります。
解消できていない部分の蓄積量が多いほど、再学習&理解にも時間がかかることで自分自身の負担にもなり、その状態を少しでも改善するには予習が必要です。
●予習を含めた学習
①あらかじめ「予習」をしておく
②学校で授業を聞くときには「復習」となり、理解度の確認も同時にできる
③理解度が低い部分があれば塾で解消していく
上記の場合、予習なしの場合と違って学校で習う際には復習&確認ができる状態となるので、授業進度に置いてけぼりになることは格段に減っていきます。
また、それでもつまずき部分があった場合は一から学び直しではなく、ポイントを絞った再学習で補えることがほとんどなので、再理解にかかる時間も少なく済みます。
これを継続していくことで、テストが近づいた時に「急いで出来ないところを全て復習いないといけない!!」といったことも無くなります。
当塾での学びにおいても、教室・家で予習を行ってから学校で同項目を学ぶような学習カリキュラムにしています。
少しでも予習をしてから学校の授業へ取り組むか否か、これは後々になっても大きな差が生じるのは明らかです。
学習塾Hope
住之江区北加賀屋5-2-9セラ鳴門(南港病院向かい)
(学習塾Hope) 2025年3月27日 19:59
意識の違いから生じること。
それは、取り組みにおける「意識の違い」から生まれる差です。
例えば、ある問題を解いていて
Aさん:「間違い箇所を確認したけど、なぜそうなるのか分からないから質問しよう。」
Bさん:「多分、ここで間違えたのだろう。大丈夫、理解した。」
ここではAさんが不明点をそのままにせずに、先生に質問することでしっかりと出来ないところを理解しようとしていますね。
逆にBさんはどうでしょう?
間違い箇所の確認はしたけど、確認した解き方で合っているのか不確かのまま終えています。
その確認作業が間違っていた場合、次に同じ問題が出たときに果たして正解できるでしょうか?
ここではBさんも自分で確認した上で、そのやり直し方や確認内容で合っているのか分からない際は、先生に聞いて解消する必要があります。
解けない問題を自分で解けるようにするには、そういった意識の積み重ねがとても大切です。
勉強ができる子は日頃より宿題をする時、学校や塾の授業の時、テスト前の確認作業の時など、あらゆる場面において勉強ができるようになるための意識を持って取り組んでいるだけです。
その意識を持つようにするには学力は関係なく、意識が変われば学習への取り組み方も変化していき、学力Upへも確実に繋がっていきます。
当塾でも生徒自身の意識を変えていく必要があるとなれば、先ずはその意識改革から徹底的に行っていきます。
意識が変わっていくタイミングは生徒それぞれで異なり、地道な道のりですが、そこが変わらなければ結果として学力も上がっていきません。
学習塾Hope
住之江区北加賀屋5-2-9(南港病院向かい)
(学習塾Hope) 2025年2月24日 17:33
インプットだけはNG
インプット学習だけで終わっていませんか?
テスト当日になって急に「どう解くんだっけ?」と、ワーク・宿題では解けていたものが結局解けなかったということはありませんか?
結局、それはアウトプットの量が不足し、しっかりと定着まで至っていない状態を指します。
インプットで知識や解き方を頭に入れていき、自分で実際に問題を解くことでアウトプットしていく。
そうすることで『何が解けて、何が理解出来ていないのか』のつまずき箇所が把握でき、再学習が必要な項目をまた復習しながら学びなおしを行っていきます。
この学びなおし・復習をどれだけ素直に行えているか、ここも大切なことです。
ここで毎回の「つまずき」をスルーして放置しておくと、どんどん溜まっていき後々になって大変しんどい思いをすることになります。
新たに学んだことを問題演習することで、適切に解けるかどうか確認していく。
その習慣を普段から意識して身につけておくことで、学習効果は大きく変わっていきます。
「ただ教わっている」「授業を聞いている」だけで成績は上がりません。
しっかりとアウトプットすることで、自分の弱点を見つけて学びなおしへ取り組んでいくことで初めて本当の定着へと繋がっていきます。
学習塾Hope
住之江区北加賀屋5-2-9(南港病院向かい)
(学習塾Hope) 2025年2月13日 13:07
レベル別問題の活用
ワークの中には基礎(A問題)・標準(B問題)・発展(C問題)等に振り分けされているものも多いと思いますが、進め方については学力層によってもちろん変わってきます。
例えば、基礎が固まっている子にとっては標準レベル以上の問題演習へ取り組んでいくことで実践力や応用力を養っていくことが必要です。
しかし第一目標として学年平均以上~70点前後の圏内を目指している層の子にとってはそう簡単にはいきません。
単純にA⇒B⇒Cと取り組むのではなく、Aを周回学習することで先ずは基礎レベルで土台をしっかりと固めていくのが優先して行うべきことです。
こう見ると皆さん、当然のことだと思うかもしれませんが、案外それが出来ていない子が多いです。
当たり前ですが、基礎が出来ていないのに標準~発展問題へは太刀打ち出来ません。
ワーク演習などでもその辺りを意識せずに基礎・標準・発展、ととりあえず何となく解いている状態ではその子にとって最適学習とは言えません。
まずは今の学習状況&理解度を自覚して、自分のレベルに適したところから集中して取り組んでいくようにしましょう。
また、テスト直前になってから焦って取り組むのではなく、普段から前もって行っておくことで、「基礎」が固まれば次は標準問題、と余裕をもって実践力をつけていくことができます。
ワーク演習の進め方が分からず捗らない時はそういったことも参考にしてみてください。
学習塾Hope
住之江区北加賀屋5-2-9(南港病院向かい)
(学習塾Hope) 2025年1月20日 18:46
やるしかない環境
今年もよろしくお願いいたします。
1月は共通テスト、2月には私立高校入試、公立高校入試(特別選抜)、3月に公立高校入試(一般選抜)と続いていきますので、受験生の皆さんは悔いを残すことがないよう最後までしっかりと日々の学習へ取り組んでいきましょう!!
さて、家で勉強する際に日々で集中して取り組めていますか?
これは全学年で共通して言えることですが、「勉強が捗らない」「勉強しても集中できない」といった状況の場合は今一度、自分の学習環境を見直してみてください。
自分の誘惑になるようなものを身の回りに置いた状態で勉強へ取り組んでいませんか?
例)スマホ・タブレット・ゲーム機器など。
学習時間に不必要なものは別の場所に置いておき、休憩時間にリビング等でそれらを使って一息するようにすれば、やる時と休む時のONとOFFの切り替えもしやすいです。
せっかく勉強へ取り組んでいるのに、スマホの通知が気になってその度に確認してスマホ操作に時間を割いていては、学習効率が格段に下がります。
真剣に日々の学習と向き合うのであれば「勉強するしかない環境」で取り組むことです。
塾に行けば先生がいて授業が始まるので自然とそういった環境になりますが、お家ではそうはいきません。
自分の誘惑になり得るものは勉強時間中だけは除外することで、学習も捗るようになり、より中身のある時間にもなります。
学習塾Hope
住之江区北加賀屋5-2-9(南港病院向かい)
(学習塾Hope) 2025年1月 6日 17:28